CATEGORY 労働基準法
-

長時間労働は何時間から?厚生労働省の基準と中小企業が今すぐすべき原因別の対策
働き方改革が推進される現代において、長時間労働は企業規模に関わらず避けて通れない課題です。特にリソースが限られる中小企業にとっては、「何時間からが長時間労働となるか」という厚生労働省の基準を理解し、具体的な対策を講じることが急務です。
この記事では、長時間労働の定義や健康リスクの基準、そして企業が直面しやすい原因を徹底的に解説します。さらに、すぐに実践できる長時間労働の解決策や具体的な対策事例をご紹介します。
より深く、具体的なアクションプランを検討したい方、他社の最新の取り組みを知りたい方は、以下のレポート「残業の実態や削減の取り組みに関する調査」をぜひご活用ください。
-

オンライン面接のマナー完全ガイド|服装・背景・通信環境・場所の注意点
しかしオンライン面接は、「移動時間や交通費がかからない」というメリットがある一方で、対面とは勝手が違うため、「どのような服装が適切か」「特有のマナーはあるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
気軽に実施できるように思えるオンライン面接ですが、画面越しであっても、服装には配慮すべきですし、「どんな背景を設定するか」「通信環境に問題はないか」といった点も評価に影響する可能性があります。
そこでこの記事では、オンライン面接で意識すべき重要なマナーについて、服装、背景、適切な場所選び、機材の確認といった観点から徹底的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
-
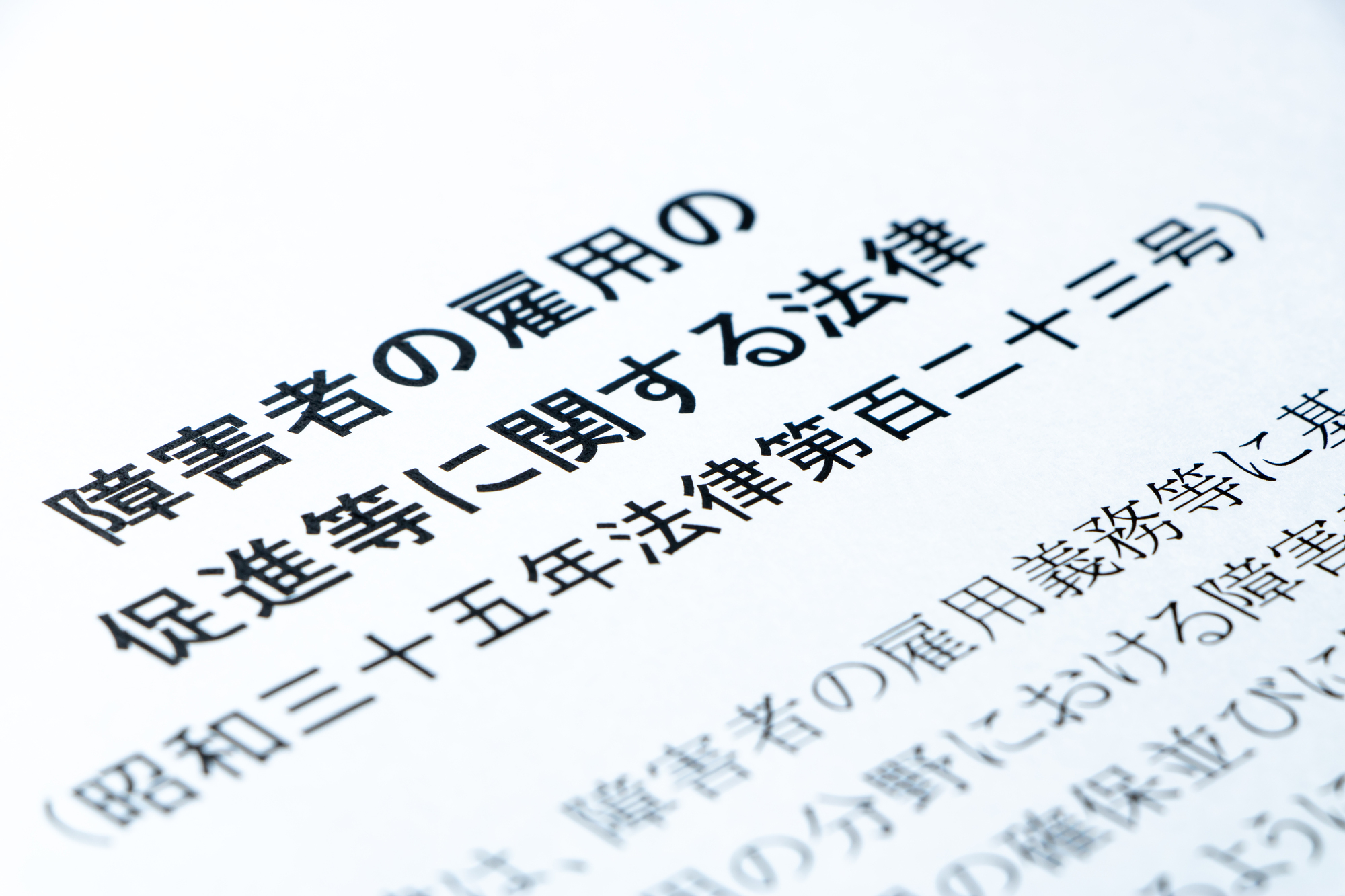
障害者雇用時のトラブル事例と解決策|中小企業ができる職場での効果的な配慮とは?
優秀な人材確保の機会となる一方で、「職場でトラブルが起きたらどうしよう」「どのように接すればよいのかわからない」といった不安から、障害者雇用に踏み切れない担当者の方も多いのではないでしょうか。
障害者雇用におけるトラブルは、多くの場合、ほんの少しの知識不足やコミュニケーションのすれ違いが原因です。
この記事では、中小企業で実際に起こりがちな障害者雇用のトラブル事例を「あるある」として具体的に紹介し、背景と具体的な解決策、未然に防ぐための効果的な配慮についてわかりやすく解説します。
障害者雇用を成功させ、企業の成長につなげるには、採用後の定着支援が不可欠です。障害の有無にかかわらず、従業員がなぜ離職してしまうのか、その理由と対策を知ることは、職場全体の環境改善につながります。
今すぐ使える離職対策のヒントが満載の資料をぜひご活用ください。
-

中小企業の勤怠管理、正しくできていますか?基本からシステム選びまで徹底解説
大企業のように専任の労務担当者や情報システム部門を置くことが難しい中小企業にとって、勤怠管理はより切実で複雑な課題をはらんでいます。
担当者がほかの業務と兼務していたり、昔ながらのExcelやタイムカードでの勤怠管理を続けていたりする中で、悩みを抱えている経営者や担当者は少なくありません。
この記事では、勤怠管理の基本的な知識から、中小企業が抱えがちな課題や最適な勤怠管理方法を見つけるための比較ポイントまで、網羅的に解説します。
-

【中小企業向け】同一労働同一賃金対策ガイド|派遣や再雇用の実務まで徹底解説
同一労働同一賃金は、同じ仕事をしているにもかかわらず、「パートだから」「派遣だから」といった雇用形態を理由に、給与や福利厚生における不合理な差を禁止するものです。
「知らなかった」では済まされず、もし従業員から「正社員と比べて待遇がおかしい、ずるい」と訴訟を起こされれば、企業の評判や採用活動に大きなダメージを与えかねません。
この記事では、中小企業の人事・労務担当者が今すぐ取り組むべき同一労働同一賃金の対策について、厚生労働省のガイドラインを基にわかりやすく解説します。賞与、派遣、定年後再雇用といった具体的なケースについても、実務的なポイントをまとめました。
-

給与計算の完全ガイド|手取り計算シミュレーションから無料ソフトまで徹底解説
給与計算は、単に従業員へ給与を支払う手続きではありません。それは、会社の根幹を支える従業員との信頼関係を築き、法令を遵守する健全な経営に不可欠な戦略的業務です。
しかし、毎年のようにおこなわれる法改正や複雑な給与計算に、多くの中小企業経営者やバックオフィス担当者が頭を悩ませているのが実情ではないでしょうか。
この記事では、そうした悩みを解決するため、給与計算の基礎知識から、業務を劇的に効率化するツール、さらには活用できる補助金制度まで、給与計算に関する情報を網羅します。
-

障害者雇用の法定雇用率、2026年に2.7%へ!中小企業の対策を計算方法から解説
2024年4月に障害者雇用の法定雇用率が2.5%に引き上げられたばかりですが、早くも次なる引き上げが目前に迫っています。2026年7月には2.7%へとさらに上昇し、これまで対象外だった中小企業も障害者雇用の義務化の対象となる可能性があります。
「うちはまだ関係ないと思っていた」「何から手をつければいいのかわからない」といったお悩みを持つ中小企業も多いのではないでしょうか。
この記事では、障害者雇用の法定雇用率の基本から、今後取り組むべき対策まで、中小企業の視点に立ってわかりやすく解説します。
-

就業規則の意見書は必須?もう迷わない記入例や意見書作成時の注意点を解説
就業規則の作成や変更に必要な「意見書」の存在は、多くの中小企業にとって、その必要性や正しい作成方法がわかりにくいものです。
労働基準法で義務付けられている就業規則の意見書は、単なる形式的な書類ではないのです。適切に作成しないと、法的なトラブルに発展したり、従業員との信頼関係を損ねる原因になったりする可能性も否めません。
意見書が不要なケースはあるのか、異議ありと書かれたらどう対応すべきかなど、この記事では、そうした疑問に答えるべく、就業規則の意見書に関して徹底解説します。
-

就業規則がない企業は違法?従業員10人以下でも作成すべき理由とリスクを解説
従業員が10人以下の場合、法的な作成義務がないため、「就業規則がない会社」も少なくありません。
しかし、就業規則がないことには、実は多くのリスクとデメリットが潜んでいます。労働時間、賃金、退職といった重要なルールが曖昧なままでは、労使間でトラブルが発生しやすくなるからです。
この記事では、従業員が安心して働ける環境を整えるため、今からでも就業規則の重要性を理解し、作成に着手できるよう解説します。
-
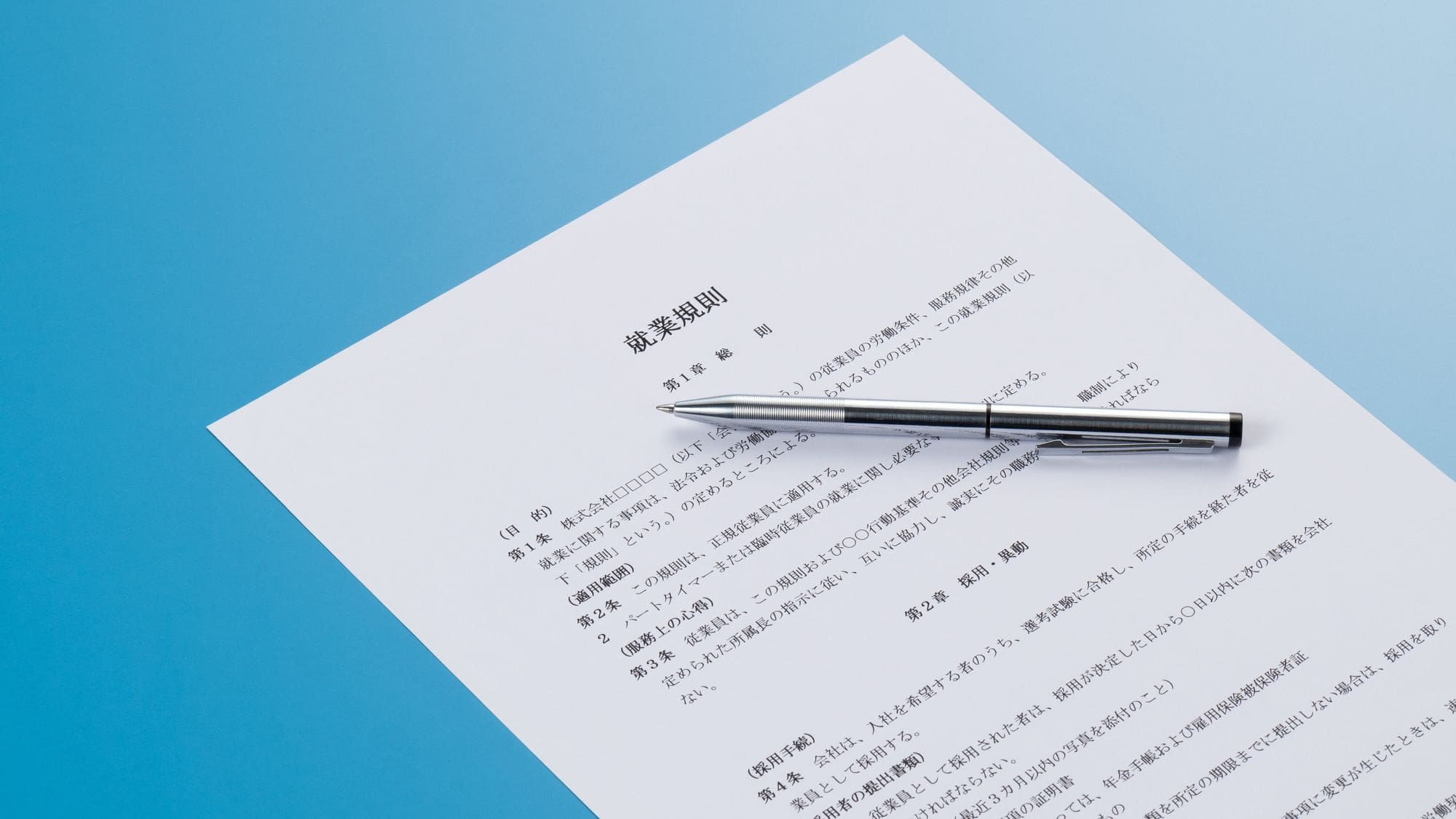
これで安心!就業規則の届出義務と変更手続き、中小企業のための完全ガイド
「就業規則」は、従業員と会社双方にとって、安心して働くための大切なルールブックです。
労働基準法で義務付けられている就業規則の作成や、労働基準監督署への届出、内容変更時の手続きは、ルールを知らないと罰金などのペナルティにつながる可能性もあります。
このガイドでは、就業規則の届出義務の基本から、届出に必要な書類や記入例まで、中小企業が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
-

障害者雇用とは?中小企業経営者が知るべき制度の基本・法定雇用率・助成金までわかりやすく解説
「障害者雇用」と聞くと、中小企業は法規制の複雑さや受け入れ体制への不安を感じるかもしれません。しかし、障害者雇用は単なる企業の義務ではなく、新たな人材の確保や、組織の多様性を高める絶好の機会となり得るのです。
少子高齢化が進み、人手不足が深刻化する現代において、障害のある方々が持つ潜在能力は、企業の成長に不可欠なものとなっています。
この記事では、障害者雇用の基本である法定雇用率から、活用できる助成金制度など、中小企業が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
-

労働条件とは?労働条件明示の義務と記載すべき内容を解説
中小企業の経営者や人事担当者にとって、「労働条件」の理解は避けて通れない重要なテーマです。従業員とのトラブルを防ぐためにも適切な対応が求められます。
この記事では、中小企業が知っておくべき労働条件の基本と、最新の法改正に対応するための実務ポイントをわかりやすく解説します。従業員との信頼関係を築くためにも、正しい情報を押さえておきましょう。
-

労働組合は意味ない?問題点、企業としての付き合い方を解説
「労働組合は意味ない」とインターネットや職場でも、そのような言葉を耳にする機会が増えています。
なぜ労働組合は「意味ない」と言われてしまうのか、本当に価値がないのかを、中小企業経営者の視点から掘り下げました。
労働組合が持つ本来の役割や現代における存在意義について、中立的な視点から解説し、とくに中小企業が労働組合とどのように向き合い、良好な関係を築いていくべきかについても具体的に考察します。
-

【これを読めばOK】就業規則の変更手続きを徹底解説!従業員10人未満でも必要?
会社のルールブックである「就業規則」。法律の改正や会社の成長に合わせて、内容変更の必要が出てくることがあります。
この記事では、就業規則の変更は何をすればよいか、 手続きの方法について解説し、従業員が10人未満の会社でも就業規則の変更は必要なのかといった疑問をお持ちの方向けに、わかりやすく、知りたい情報を網羅していきます。
-
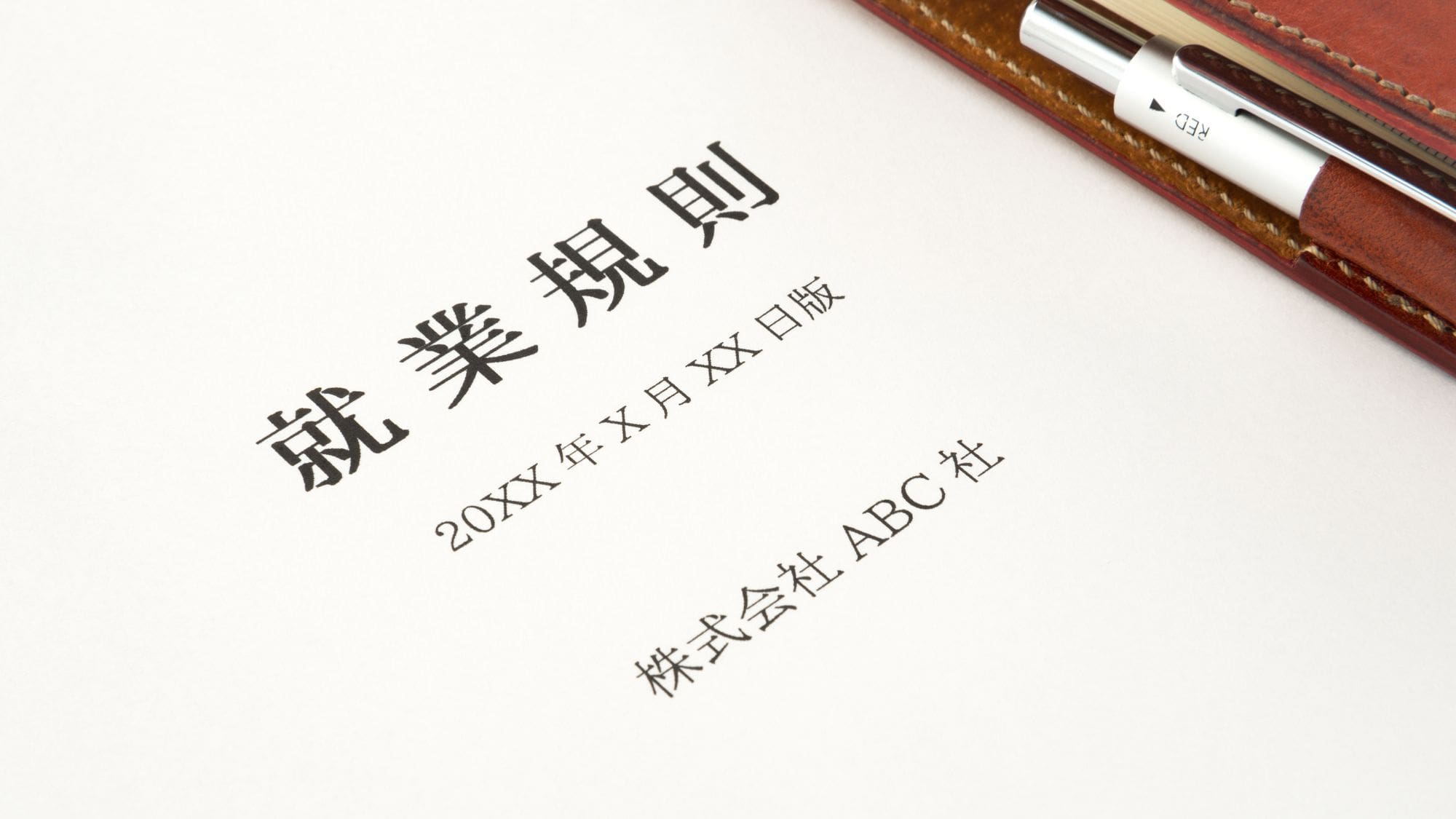
就業規則とは?労働基準法とどちらが優先される?2つの関係を正しく理解しよう
労働者の働き方と企業の経営において、就業規則とは労働基準法と切っても切れない関係にあります。
就業規則とは職場のルールブックとして、労働条件や規律を明確に定めるものですが、その内容は労働基準法が定める最低基準を満たしている必要があるのです。
両者の関係性を正しく理解しないまま運用すると、知らず知らずのうちに法令違反を犯し、労使トラブルや予期せぬリスクに直面する可能性があります。
この記事では、就業規則と労働基準法の基本的な関係から、就業規則に必ず記載すべき事項、作成・変更の手順、違反した場合のリスク、そしてトラブルを防ぐために中小企業ができることまでをわかりやすく解説します。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録






